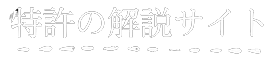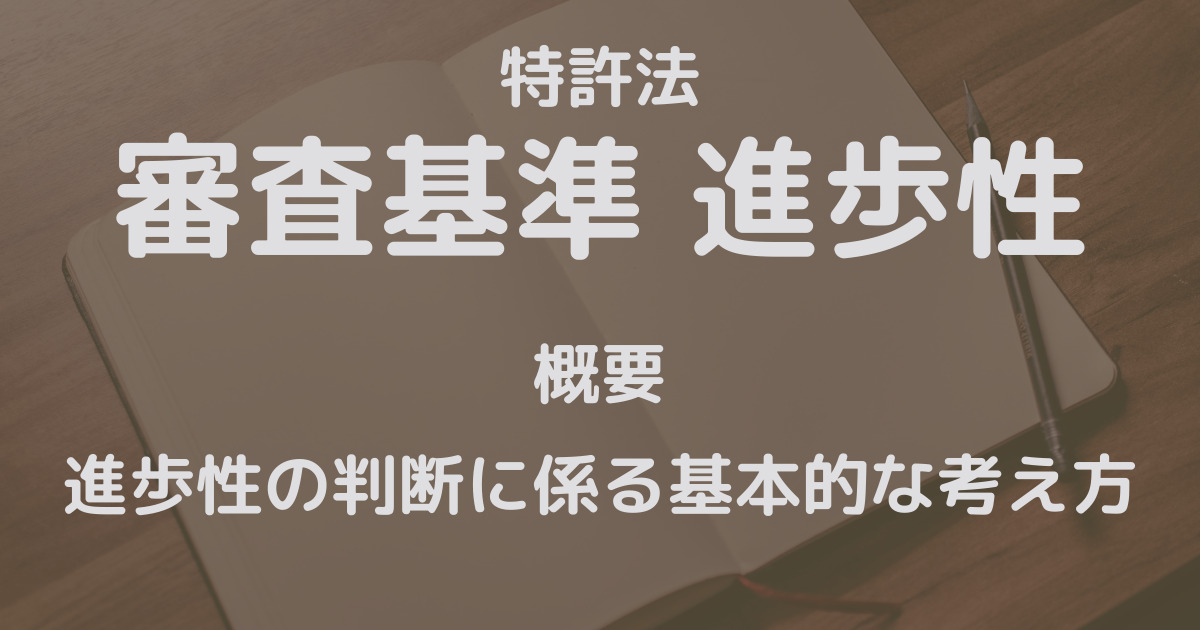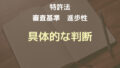特許実務では、進歩性はとても重要です。
この記事では、特許の審査基準の進歩性(特許法第29条第2項)について勉強したいと思います。
進歩性の拒絶理由を通知された場合、審査官の判断は正しいのかな?と疑問に思うことや、拒絶理由に納得できない場合がありませんか?
私は、弁理士になり、進歩性の拒絶理由が通知される度に、悩み、そして解決の道を探ります。審査官の判断に誤りがあることもあります。その場合は、意見書で反論します。
この記事では、特許の審査基準に即して、進歩性について今一度復習したいと思います。まずは、概要欄から丁寧に説明します。
結論をいうと、審査基準の「進歩性」の「概要」欄においては、進歩性の判断の手法について、記載されています。また、「進歩性の判断に係る基本的な考え方」欄では、論理付けや、当業者、周知技術、慣用技術、論理付けの試み方の説明が記載されています。
審査基準の進歩性の「概要」
では、早速、審査基準の進歩性の「概要」欄から説明します。
審査基準の「進歩性」の「概要」欄においては、進歩性の判断の手法(取り扱い方)について、記載されています。つまり、審査基準の「進歩性」の欄は、審査官が、発明について、進歩性の判断をどのように判断しているのかが記載されています。
よって、この審査基準の進歩性を勉強することは、実務者にとって非常に重要です。
私は、出願書類作成時、進歩性の拒絶理由の反論を考える際、審査基準を参照して、いつも検討しています。
特許査定を得るためには、審査官の審査を通らなければなりませんので、まずは、審査基準の進歩性を理解することは、とても重要になります。
進歩性の制度趣旨
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない(特許法第29条第2項)。
進歩性の条文(特許法第29条第2項)が規定されている理由は、当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからです。
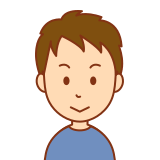
「技術進歩に役立たず、かえってその妨げになる」ので、進歩性のない発明には特許を付与しないという制度趣旨です。
審査基準の「進歩性の判断に係る基本的な考え方」
進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明
まず、進歩性の判断対象となる発明は、請求項に係る発明になります。つまり、請求項の単位で進歩性を判断します。
したがって、
【請求項1】
A処理手段を含む情報システム。
【請求項2】
請求項1において、
B処理手段を更に含む情報システム。
のように、2つの請求項がある場合、請求項1、請求項2それぞれについて進歩性の判断がなされます。
したがって、例えば、請求項1に進歩性がない場合であっても、請求項2に進歩性がある場合もあります。
論理の構築(論理付け)の説明
審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行います。
先行技術とは、特許出願時よりも前に公になった文献等を示します。
論理の構築(論理付け)とは、 容易に想到できたことの論理の構築(論理付け) です。
当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、
- 進歩性が否定される方向に働く諸事実
- 進歩性が肯定される方向に働く諸事実
を総合的に評価することが必要とされます。そして、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することによって論理的に行うことを意味しています。
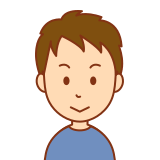
審査官は、個人の感覚や主観などで、評価してはいけない、ということです。
つまり、審査官の違いによって、進歩性の有無が異なる判断にならないようにしています。
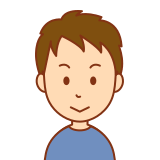
とはいっても、審査官によって進歩性の判断は様々です。
実際は、進歩性の判断が厳しい審査官もいれば、緩い審査官もいます。
当業者の説明
「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された者をいう。 (i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有していること。 (ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。 (iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。 (iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること。(審査基準の「進歩性」)
実際には、審査官が進歩性の判断を行いますが、審査官が当業者を想定して進歩性を判断します。
つまり、審査官は、出願時の当業者を想像し、もし、自分(審査官)が出願時の当業者だったら、発明を容易に想到できたか?を検討することになります。
実際の審査で問題となるのは、この「出願時」の当業者であることです。です。審査官の審査時ではない点に注意が必要です。審査官が審査する審査時は、出願時よりも技術水準が向上しているので、進歩性のしきい値が高くなります。
つまり、審査官は、出願時の当業者で容易想到性を判断しなければなりません。
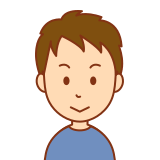
出願時で判断することが重要です
当業者は、「専門家からなるチーム」でもOK
審査基準には、「当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。」と記載されています。
技術常識とは当業者に一般に知られている技術又は経験則から明らかな事項
まず、技術常識とは、
- 当業者に一般に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む)。
又は
- 経験則から明らかな事項
を言います。
また、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれます。
当業者に一般的に知られているものであるか否かは、文献数のみで判断されるだけでなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮される、という点に注意が必要です。
周知技術とは、その技術分野において一般的に知られている技術
「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術です。
例えば、
(1)その技術に関し、相当多数の刊行物又はウェブページ等が存在しているもの
(2)業界に知れ渡っているもの
(3)その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの
慣用技術とは、 周知技術であって、かつ、よく用いられている技術
「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術です。
技術水準
「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成されます。
論理付けの試み方
審査基準には、審査官の論理の試み方が記載されています。
まず、論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握します。
そして、請求項に係る発明についての知識を有しないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みます。
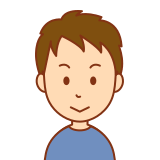
つまり、審査官は、出願時の当業者を想像します。そして、「請求項に係る発明」は、容易に想到できるか?という点を論理的に考えます。
まとめ
審査基準の「進歩性」の「概要」欄においては、進歩性の判断の手法について、記載されています。また、「進歩性の判断に係る基本的な考え方」欄では、論理付けや、当業者、周知技術、慣用技術の説明、論理付けの試み方が記載されています。